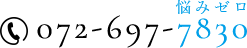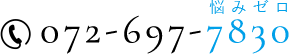ケロイド・傷跡とは
 ケロイドや傷跡は、皮膚が損傷を受けた後の修復過程で生じる病変です。正常な傷の治癒過程では目立たない傷跡となりますが、体質や傷の状態により、盛り上がった目立つ傷跡として残ることがあります。これらは肥厚性瘢痕とケロイドに大別され、それぞれに異なる特徴があります。
ケロイドや傷跡は、皮膚が損傷を受けた後の修復過程で生じる病変です。正常な傷の治癒過程では目立たない傷跡となりますが、体質や傷の状態により、盛り上がった目立つ傷跡として残ることがあります。これらは肥厚性瘢痕とケロイドに大別され、それぞれに異なる特徴があります。
傷跡(肥厚性瘢痕)
肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん)は、傷が治る過程で皮膚が盛り上がって残る傷跡です。傷の範囲内にとどまり、時間経過とともに徐々に平坦化していく傾向があります。数年かけて自然に改善することが多いのが特徴です。
ケロイド
ケロイドは、傷跡が元の傷の範囲を超えて周囲の正常な皮膚にまで広がっていく病変です。
赤く盛り上がり、かゆみや痛みを伴うことが多く、自然に改善することはほとんどありません。むしろ時間とともに大きくなる傾向があり、見た目だけでなく機能的な問題を引き起こすこともあります。
ケロイドの原因は?
ケロイドの発生には体質的な要因が大きく関わっています。
外傷
 手術、外傷、やけど、ニキビ、虫刺され、予防接種などの皮膚への刺激がきっかけとなります。特に皮膚の緊張が強い部位や、動きの多い関節部では発生しやすくなります。
手術、外傷、やけど、ニキビ、虫刺され、予防接種などの皮膚への刺激がきっかけとなります。特に皮膚の緊張が強い部位や、動きの多い関節部では発生しやすくなります。
遺伝的要因
家族内でケロイドができやすい体質が遺伝することがあります。両親にケロイド体質がある場合、子どもにも同様の体質が現れる可能性が高くなります。
その他の要因
思春期から30歳頃までの若い世代に発症しやすく、ホルモンバランスの影響も示唆されています。また、黒色人種や黄色人種など皮膚の色が濃い人種に多い傾向があります。高血圧が重症化に影響するとも言われています。
ケロイドの症状と
できやすい部位
ケロイドは特徴的な症状を示し、発生しやすい部位にも傾向があります。これらを理解することで、早期の発見と適切な対処が可能になります。
症状
ケロイドはピンク色から赤色の扁平または半球状の隆起として現れます。かゆみや痛み、引きつれ感などの症状を伴い、横から圧迫すると痛みを感じることが特徴的です。
時間の経過とともに徐々に拡大し、元の傷の範囲を超えて広がっていきます。つまんだ際に軽い痛みを生じ、時にはかゆみが強くなる場合もあります。これらの症状により、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
できやすい部位
胸部、肩などが代表的な好発部位です。これらは皮膚の緊張が強い部位であることが共通しています。
一方、顔面、頭部、手足の先端、下腿などには発生しにくいとされています。皮膚の緊張度の違いが、ケロイドの発生に大きく影響していると考えられています。
ケロイドがある場合、その部位への過度な負荷は避ける必要があります。例えば、胸部にケロイドがある方の腕立て伏せや腹部手術後の腹筋運動などは、患部の皮膚が緊張を繰り返すため、症状を悪化させる可能性があります。
ケロイド体質の見分け方
ニキビ跡が盛り上がりやすい方は、ケロイド体質の可能性があります。ニキビも皮膚への小さな損傷であり、これが盛り上がって治る傾向がある場合、わずかな傷でもケロイドを形成しやすい体質である可能性が高いと言えます。
家族や親戚にケロイド体質の方がいる場合も注意が必要です。ケロイド体質には遺伝的な要因が関与していると考えられており、血縁者に同様の体質を持つ方がいれば、自身も同様の体質を持っている可能性があります。
アレルギー体質の方にケロイド体質が見られることも少なくありません。アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー疾患をお持ちの方は、ケロイドが発生しやすい傾向があるため、ケガや手術の際は、特に慎重なアフターケアが必要です。
ケロイドは治らない?
治療法について
ケロイドは完全に治すことは困難ですが、適切な治療により症状の改善が期待できます。
内服薬
トラニラスト(リザベン)という抗アレルギー薬を内服し、ケロイドによる炎症を抑えます。かゆみの軽減にも効果があり、長期間の服用により改善が期待できます。
外用薬
ステロイド軟膏やテープを使用し、炎症を抑えて平坦化を図ります。ヘパリン類似物質を含む保湿剤も併用し、皮膚の柔軟性を保ちます。
圧迫療法
サポーターや包帯などで患部を圧迫し、過剰な血流や炎症を抑制します。
局所注射
ステロイドをケロイド内に直接注射し、炎症を抑えて縮小を図ります。月に1回程度の頻度で、複数回の治療が必要です。効果は高いですが、痛みを伴うため局所麻酔を併用することもあります。
手術療法
大きなケロイドや他の治療で改善しない場合は、外科的切除を行います。ただし、単純な切除だけでは再発率が高いため、皮弁移植や植皮術で欠損した皮膚を補います。術後は放射線治療や圧迫療法を併用することが重要です。