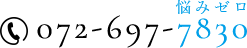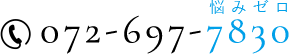脂肪腫(リポーマ)とは
脂肪腫は、皮下組織に発生するやわらかい腫瘍です。良性腫瘍の中では発生頻度が高い疾患です。発生時期は幼少期と考えられていますが、成長速度が緩やかなため、多くの場合40~50歳代で発見されます。20歳以下での発見は稀です。
サイズは数ミリのものから直径10cmを超える大きなものまでさまざまで、通常は痛みなどの自覚症状はありません。弾力があり、指で押すと少し動くのが特徴的です。背中、肩、頚部にできることが多く、上腕や臀部、大腿など四肢の体幹に近いところにも見られます。顔面や頭皮、下腿、足などへの発生は比較的少ないです。
単発性の腫瘍として現れることが多いですが、稀に複数箇所に発生することもあります。良性腫瘍ではありますが、大きなものの中には悪性の可能性も含まれるため、専門的な検査が必要な場合があります。自然に消失することはなく、徐々に大きくなる傾向があるため、早期の対応が推奨されます。
脂肪腫の原因は?
脂肪腫が形成される明確なメカニズムは、現在のところ完全には解明されていません。
発生の要因として、衣服や下着による摩擦など、日常的な刺激を受けやすい部位に形成される傾向があることが分かっています。
染色体の異常も重要な要因として指摘されています。脂肪腫の中には染色体異常が確認されるケースがあり、毛細血管の周囲に残る未分化の細胞が、何らかのきっかけで脂肪細胞に変化して増殖することが原因と考えられています。成熟した脂肪細胞は増殖しませんが、成人後も残存している未分化細胞が遺伝子の異常により脂肪細胞へ分化・増殖すると考えられています。
その他、ストレスや肥満、生活習慣などとの関連も指摘されていますが、発生の根本的な原因については研究が続けられています。
脂肪腫ができやすい人
脂肪腫が発生しやすい方には、いくつかの共通する特徴があります。
肥満・生活習慣病を
お持ちの方
 肥満の方は脂肪腫のリスクが高まる傾向にあります。脂肪細胞が集まって形成される腫瘍であるため、過体重の状態は発生の要因として作用する可能性があります。
肥満の方は脂肪腫のリスクが高まる傾向にあります。脂肪細胞が集まって形成される腫瘍であるため、過体重の状態は発生の要因として作用する可能性があります。
糖尿病や高脂血症といった生活習慣病も関連することがあります。血液中の脂質が増加した状態では、血管壁への脂肪の沈着が起こりやすくなります。これらの疾患を持つ方は、脂質の多い食事を習慣的に摂取している傾向があり、脂肪代謝に異常をきたしている可能性があります。
性別・年齢による特徴
女性に多く見られる傾向があります。女性ホルモンであるエストロゲンには脂肪細胞の成長を促進する働きがあるため、男性と比較して脂肪細胞の増殖や蓄積が起こりやすいと考えられています。
発見される年齢は40~60代に多く、ゆっくりと成長するため若い頃には気づかず、中高年になってから受診される方が多いのが特徴です。
家族歴のある方
家族で脂肪腫が発生している方がいる場合、発症リスクが上昇する可能性があります。遺伝子の異常が関係すると考えられていますが、必ず遺伝するものではありません。
脂肪腫と悪性腫瘍の見分け方~急に大きくなることも
ある?~
脂肪腫は良性腫瘍ですが、似た症状を示す脂肪肉腫という悪性腫瘍もあります。初期段階では「やわらかいしこり」「痛みがない」といった共通の症状があるため、見た目だけでは区別がつかないことがあります。
両者を見分ける重要なポイントは成長速度です。脂肪腫は時間をかけてゆっくりと大きくなりますが、脂肪肉腫は短期間で急激に増大する特徴があります。数ヶ月間で数cm以上、目に見えて大きくなった場合は、悪性の可能性を考慮する必要があります。
その他にも注意すべき特徴があります。10cmを超える大きさの腫瘍、硬く周囲と癒着しているもの、痛みやしびれを伴うもの、太ももに発生したもの、表面が硬く皮膚が赤くなったり変色があったりするものは、脂肪肉腫の可能性を考慮した診断が必要です。圧痛やしびれなどの症状が現れた場合は、専門医による早急な診察が必要です。
確定診断には医療機関での検査が不可欠です。超音波検査で大きさや構造を確認し、深部の広がりや浸潤の有無を調べるためにMRIやCT検査を行います。その場合は提携病院をご紹介します。
最終的には切除した組織の病理検査により、細胞を顕微鏡で観察して良性・悪性の確定診断を行います。3cm以上のしこりや急に大きくなったしこりは、「痛みがないから大丈夫」と自己判断せず、医師の診断を受けることが大切です。
脂肪腫は自分で取るのは
不可能!?脂肪種の手術
脂肪腫は皮膚の下に生じる脂肪の塊で、押しても小さくなることはなく、自分で取ることはできません。内容物が液状ではないため、時々「押して膿を出した」という話を聞くことがありますが、別の種類のできものだと考えられます。
自然に消失することはなく、内服薬や外用薬での治癒もできないため、外科手術による摘出が唯一の治療法となります。手術では腫瘍を包む薄い膜を破らないように取り除きます。部分的に腫瘍が体内に残ると再発のリスクが高まるため、膜ごとすべて摘出することが重要です。
手術の流れとしては、皮膚を切開し、周囲の組織から丁寧に剥離して腫瘍を摘出します。その後、出血を十分に止めてから縫合し、圧迫固定を施して手術を終了します。放置すると徐々に大きくなり、大きくなるほど切開範囲が広がるため、傷跡が目立ちやすくなります。小さいうちに治療することで、体への負担も軽減でき、傷跡も小さく済むため、早めの受診が推奨されます。