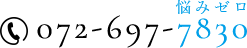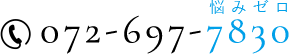乾癬とは
 乾癬(かんせん)は、皮膚が赤く盛り上がり、その表面に銀白色のフケ状の皮膚片が付着して剥がれ落ちる慢性の皮膚疾患です。「かんせん」という名前から誤解されやすいですが、他の人にうつる病気ではありません。
乾癬(かんせん)は、皮膚が赤く盛り上がり、その表面に銀白色のフケ状の皮膚片が付着して剥がれ落ちる慢性の皮膚疾患です。「かんせん」という名前から誤解されやすいですが、他の人にうつる病気ではありません。
皮膚では通常、表皮が生まれ変わって古いものが角質として剥がれ落ちるサイクルがありますが、乾癬ではこの速度が通常の10倍以上に早まってしまいます。そのため、皮膚が厚く積み重なって赤く盛り上がり、銀白色の鱗屑(りんせつ)と呼ばれるカサカサしたものがポロポロと落ちる状態になります。
症状が出やすい部位は、肘や膝、頭皮、腰からおしりなど、擦れやすく刺激を受けやすい場所ですが、全身のどこにでも現れる可能性があります。爪にも変化が見られることがあり、先端から浮き上がったり、表面に凹凸ができたりします。
乾癬の原因は?うつる?
乾癬の発症メカニズムはまだ完全には解明されていませんが、免疫機能の異常が大きく関与していることが分かってきています。
乾癬になりやすい体質の人に、感染症や精神的ストレス、薬剤などのさまざまな環境要因が加わることで発症すると考えられています。また、糖尿病や脂質異常症、肥満といった生活習慣病も症状に影響を与えるとされています。
遺伝的な要因もありますが、家族内で発症する頻度は約5%程度と報告されており、過度に心配する必要はありません。乾癬になりやすい体質は遺伝する可能性がありますが、必ず発症するわけではありません。 乾癬は感染症ではないため、触れたり、温泉やプールを一緒に利用したりしても、他の人にうつることは絶対にありません。この点は誤解されやすいため、正しい理解が大切です。
乾癬の種類と症状
尋常性乾癬
尋常性乾癬は「尋常」という普通を意味する名前の通り、全体の約70~80%を占める最も基本的な病型で、多くの患者様がこのタイプに該当します。
症状
皮膚が赤くなる紅斑(こうはん)、皮膚が盛り上がる浸潤・肥厚(しんじゅん・ひこう)、銀白色のフケのような鱗屑(りんせつ)が付着して剝がれ落ちるという特徴があります。頭皮や髪の生え際、ひじ、ひざ、おしり、太もも、すねなど外部からの刺激を受けやすい部位によく見られます。
最初は直径数ミリ程度の小さな発疹から始まり、次第に乾癬特有の赤く盛り上がった発疹となります。爪にも症状が現れることがあり、40~80%の患者様で爪の変化が見られます。かゆみは約50%の患者様で認められます。
乾癬性関節炎
関節症性乾癬とも呼ばれ、乾癬の皮膚症状に加えて関節の炎症を伴うタイプです。乾癬患者様の約15%に合併すると言われています。多くは関節症状が出る前、または同時に皮膚症状が現れますが、皮膚症状が遅れて現れることもあります。
症状
手足の関節、首から背骨、アキレス腱、足の裏などに痛みや腫れ、こわばりが生じます。特に手や足の指先の関節に腫れや変形、痛みが現れることが多いです。背中や首のこわばり、骨盤の痛みで歩きにくくなることもあります。爪に乾癬の症状がある場合は、関節炎を起こしやすいとされています。関節の症状は関節リウマチに似ていますが、異なる疾患です。
滴状乾癬
小児や若年者に多く見られ、乾癬患者の約4%に発症するタイプです。風邪や扁桃炎などの感染症がきっかけで発症することが多いのが特徴です。
症状
直径0.5~2cm程度の小さな水滴大の発疹が全身に現れます。尋常性乾癬のような厚い鱗屑は少なく、小さな赤い発疹が体中に散らばったように見えます。きっかけとなった感染症を治療することで症状は治まることが多いですが、稀に再発を繰り返し、尋常性乾癬に移行することもあります。
乾癬性紅皮症
尋常性乾癬が全身に広がった重症型で、乾癬全体の約1%に見られます。乾癬の治療が不十分だった場合に発症することがあります。
症状
全身の90%以上の皮膚が赤みを帯び、細かい鱗屑が剝がれ落ちる紅皮症の状態になります。発熱や悪寒、倦怠感などの全身症状を伴います。皮膚のバリア機能が広範囲で失われるため、体温調節が困難になったり、体液バランスが崩れたりすることもあります。
膿疱性乾癬
乾癬の中でも特殊なタイプで、膿を含んだ小さな袋(膿疱)が多数現れるのが特徴です。この膿疱には細菌は含まれていないため、周囲の人にうつることはありません。
症状
発熱とともに皮膚の発赤と膿疱が現れます。発疹が手のひらや足の裏、指先など一部だけに見られる限局型と、急な発熱とともに全身に発赤と膿疱が現れる汎発性膿疱性乾癬があります。汎発性の場合は重症で、ほとんどの患者様で入院治療が必要となります。汎発性膿疱性乾癬は厚生労働省の指定難病に指定されています。
乾癬の治療
乾癬の治療は、症状の程度や範囲、患者様のライフスタイルに応じて選択されます。
外用薬
炎症を抑えるステロイド外用薬と、皮膚の異常な角化を抑制する活性型ビタミンD3外用薬が基本となります。最近では両者を配合した合剤も開発され、塗布の手間が軽減されています。
内服薬
PDE4阻害剤という薬で炎症を抑えます。皮膚症状だけでなく関節症状や爪症状の改善も期待できます。その他、免疫抑制剤やビタミンA誘導体などを用いる場合もあります。
光線(紫外線)療法
ナローバンドUVBやエキシマライトなどの紫外線を照射する治療です。週2~3回の通院が推奨されています。病変部のみに照射できるため、体への負担が少ない治療法として広く用いられています。
生物学的製剤(注射薬)
炎症を引き起こす特定のタンパク質の働きを抑える薬剤です。他の治療で効果が不十分な場合に選択され、高い治療効果が期待できます。一方で全身性の副作用の管理が必要となるため、必要に応じて大学病院などの認定施設に紹介したうえでの投与となります。
日常生活でできること
 乾癬の症状をコントロールするためには生活習慣の改善が重要で、特に肥満やメタボリックシンドロームの改善により症状が軽減することが知られています。バランスの良い食事を心がけ、適正体重を維持することが大切です。
乾癬の症状をコントロールするためには生活習慣の改善が重要で、特に肥満やメタボリックシンドロームの改善により症状が軽減することが知られています。バランスの良い食事を心がけ、適正体重を維持することが大切です。
喫煙や過度の飲酒は症状を悪化させる要因となるため、禁煙・節酒を心がけましょう。ストレスも症状に影響するため、十分な睡眠をとり、規則正しい生活リズムを保つことが推奨されます。
皮膚への刺激を避けることも大切です。締め付けのきつい服装は避け、入浴時は強く擦らず優しく洗うようにしましょう。皮膚の乾燥を防ぐため、保湿ケアも重要です。
適度な運動は体質改善につながり、症状の改善が期待できます。ただし、運動後の汗はきちんと拭き取り、清潔を保つようにしましょう。